合気道技法と気
この文章の原文は、1993年11月に発行された「SPORTS SCIENCES」誌の【特集:「気」を考える】に、「合気道における気について」のタイトルで、警視庁在職当時の井上館長が寄稿したものです。日心館合気道の源流となる塩田剛三先生の説く合気道の気と技法に関する理念がわかりやすくまとめられていますので、ここに加除修正の上、改題して抄録を掲載します。
合気道技法と気 ~合気即生活の視点から~
1. 合気道の本質
合気道は、自然の理念に逆らうことが全くない。その字の如く「気を合するの道」である。技術面でみれば、相手の引く力、押す力、止まる力に自分の力を合わせ、相手の力を利用して制するものである。つまり、「出ようとする気持ち」
「引こうとする気持ち」に自分の「気持ちを合わす」のであり、さらに深く考えれば、「気持ちを合わす」ということ
は、相手の気持ちと一体になることである。
それはあくまでも相克ではなく、「仲良くなる」ことであり、相手を傷つけ倒すことが目的ではなく、相手に和する心を持つ人格を完成させることが目標となるのである。人格完成を目指して努力する姿こそ修行者として尊いのである。
その上、合気道の稽古は、対人関係だけでなく、大なる気、大気、つまり自然に合する修行道でなければならない。天地と一体になることが自然のリズムに生きられる。「自然即自己」という境地に達する修行道である。
合気道の技においても、自然であることは、無理がないことであり、逆に無理と思われる動作は、合気道ではないといっても過言ではない。
いかなる場合、いかなる物事、いかなる人物にも合わせ得るためには、自らに大きな和の心が必要であり、そこには、強さの裏付けがなくてはならない。その強さは、激しい修行によってのみ培われた肉体と心にあるものであり、妥協できない絶対な正しさ、貫き通した心そのものである。
そうして、そこにこそ真の和が生まれてくるのである。
インド思想では、「解脱の境地を得るには、自然な宇宙の森羅万象、宇宙そのものと合体しなければならない。」(カータカ奥義書)、あるいは「人もし自我において万有を感じ、万有の上に自我を感ぜば、それより以降は世に畏るべきものならん」(イーシャ奥義書)というように、「梵=宇宙の支配原理」と「我=個人の支配原理」の一致をはたせば超人たりうる「梵我一如」の哲学を説いている。
これは、合気道における「我即宇宙」の絶対不敗の境地と一致する。
要するに、人間がこの世にある以上、自然と一体となることの大切さを、身をもって教え導いてくれるのが合気道であ
る。
このすばらしき体験を多くの人々に味わってもらいたいものである。

2. 気とは何か
「気」の研究については、近年取り沙汰される機会が多くなったが、決して今に始まったことではない。古くは中国の春秋の頃であろうといわれている。
つまり「気」という考え方が最初に文献に表れたのは、易における、陰陽二気としてであった。天と地に代表される陰陽の二気は、互いに対立しながら循環流動して、この世の事象一切に生成と消滅を引き起こしつつ前に進めていくもので、宇宙の生成発展の原理と考えられている。易の世界観に従えば、人間本来、宇宙の気の運行と深く結ばれた存在である。
人間の心身は、小さな宇宙であって、その底には、大宇宙のエネルギーの根源とつながった深い領域がある。その見えない繋がりを知るのが易の哲学の目的といわれている。
この考え方は五行説に結びつき、老子の道家思想に影響を与え、また儒教に取り入れられて朱子の理気二元論へと発展する。
気が精神面に最初に適用されるのは、孟子における「浩然の気」である。孟子における気は、人間の体に充満しているとされるだけではなく、それを正しく養うことに依って、天地の気と通じ、合一すると考えられていた。天地の気は、一定の法則によって進行し動いている。その正しい気の運動の法則に合致すれば、人間の正しさ、つまり正義を実現することができるし、逆に人間が正しい行為によって内なる気を病まない道を実現していけば、天地の気の正しい運行に配することができる、という思想である。
かくして、孟子においては明らかに「天人合一」の思想が前面に表れるとともに、人間における道徳的な義や道が天地自然の理法と合致するところに実現されるという思想が、気の概念によって説明されると解される。
また、中国古来の宗教である、儒教、道教、仏教にはいずれも気の訓練を中心として修業法が伝えられている。
道教の場合「気」という言葉は、「神、気、精」と並列して用いられ「三河」(サンホー)と呼ばれている。「精」は肉体の本能と結び付いた時の気の状態。また「神」は訓練によって純粋な状態にまで高められた状態をいう。つまり「気」は生命の力であり、また「精」は生殖の力、そして「神」は霊妙な力といえる。神、気、精の流れは身体の生理的側面に影響を及ぼすと共に、心理的作用の変化の過程を表現している。
また、橋本左内(幕末の福井藩の儒学者)は「気とは、人に負けぬ心立ありて、恥辱のことを無念に思うところより起こる意気張りの事也」。左内の例にみられる様に、志とか、気とかいうのは人間形成の初期段階の必須の徳目なのである。
気力とか勇気とかの精神要素は科学することはできない。科学することができないものは、知識とはなり得ない。知識の伝達のみから組み立てられている現在の学校教育に気力とか勇気とかが取り上げられない理由である。
学校生活にも実生活を組み入れるべきである。それは作業教育を取り入れることである。運動選手に不良が少ないのは、実生活原理を体得した余徳である。
人間が命を保つために最も重要な要素が「気」であり、万物すべて気より生じている。「天地の理」に最も適い、「自然の理」に逆らわない状態にある時に「気」は最も充実し安定するのである。邪心を捨て天地自然のままの状態になれば
「気」は充実し、相手もその気に巻き込まれてしまう。これこそ、「我即宇宙」の境地で合気道における絶対不敗の心と一致する。
「気の流れ」「気を出す」「気を導く」「気で押える」「気が強い」「気を引く」「気を使う」「気を紛らわす」「気がつく」「気まずい」とみてくると、主体の精神活動を「気」といっていることが判る。
気のあり方の大切さを根本にしているのは、合気道に限ったことではないが、武道が人対人とのかかわりである以上、相手の気を知り、捉え、自らの気を身体に満ちみちとし、しかも自然体であることである。
気―心と身体を一つに結び付けている生命体に得たエネルギーである。気の働きは心と身体、心理作用と生理作用の両方と関係を持っている。
中国の後漢の許慎という人が著した「説文解字」は最も古い漢字研究の根本文献であるが、それによると、この時の構成要素である「气」は「霊気」であるという。
霊気は、空中に浮かぶ雲であり、あるいは雲のように空中に現れる気のことである。
雲は目に見えるが、その雲になる「もと」のものが気で、眼に見えたり、見えなかったりするが、そのように働いているものが空中にあるからこれを「霊気」といったのであろう。
塩田剛三館長は「合気道修行」(竹内書店新社)の中で「気とはバランスの結集」として次の様にいっておられる。
『合気道では、気という言葉をよく使います。この頃では、皆さんなにかというとすぐに気を持ち出して、神秘的にしてしまうのですが、合気道でいう気とは、触れずに人を投げ飛ばすといったものとは、ちょっと違うのです。私は、気とは‘バランスの結集’だと考えています。正しい姿勢と呼吸、それに集中力から生まれる爆発力。中心線の力もそうだし、タイミングも気の中に入れていいと思います。つまり、合気道では自分と相手の間で生じるすべてのことを、気としてとらえているのです。気を合せるというのはつまりそういうことで、単に気持の問題ではなく、すべての要素を一致させるということなのです。』
では、合気道における「気の使い方」を、具体的な技法に照らし合わせながら説明を進めたい。
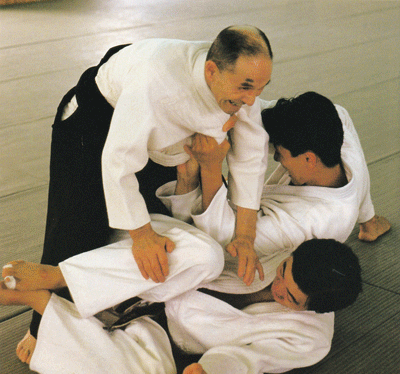
© (株) ミツルギ/撮影・小林洋
3.合気道の技と習得
小さな力で大なるものを倒す―これは誰しも願うところであり、その効果を最大限に出し得る様究明されたのがすなわち技である。
ア)基本技
約三千手の多きを数える技の中でも、特に150本の基本技を反復稽古することによって、全般に通ずるようになる。基本技の中には、手技(てわざ)が他の足技等に比して多い割合を占めている。これは合気道の技法が剣の働きを基として作られたものが多いためでもあるが、技を施す場合、足を地から離したり上体を極端に傾けたりすることは安定を欠くことになり、相手に対する機敏性を失うことになるからである。
イ)技の名称
数千を数える技の一本々々を名付けることは不可能に近く、したがって基本技だけに名称を付しているが、中には一ヶ条、二ヶ条、・・・というように、一般の人の中にはその名称だけでは動き(技の内容)を理解し難いものがある。しかし、実際に稽古を積めば、名称も難なく整理できるようになる。
他の武道でも古書等に非常に難解で高度な名称や解説が付されているが、それは武術そのものが高度なものである上に他者に其の秘密を盗まれる事を防ぐためのものであったと思われる。また、武術家が禅宗等の宗教家(僧侶)の手を借りて書き残されたからであろう。合気道も同様のことが考えられるのである。
ウ)稽古法
合気道の稽古は激しく、また柔らかくもどの様にも行うことができるので、老若男女を問わず、全ての人が行いうるものである。稽古は武道そのものを求めて行うのが当然であるが、他に健康法のため、また護身のため精神修養のため、あるいは美容のためにそれを求めてもよい。合気道は、さほどの体力を必要としな
い。両手で8キロ程度の物が持ち上げられる力があれば充分である。つまり決して無理のない技法の集積であるからである。
技を施す時に必要以上に大きな力を必要とするのは、自分の技が不適格であり不自然であるためである。通常の稽古では、試合形式をとらずに形の反復稽古を行う。形といっても生きた形であって、即実際に役立つものでなければならない。また、一般のスポーツと異なり、試合の勝敗という相対的なものを求めるのではなく、絶対的なものを求める姿がその在り方である。
無論、相手を制することを無視することなく、しかも超越的な強さへの求道でなければならない。そのことが前述した(和)の精神に結びつくことになる。つまり、稽古をしている者同志で一つの技を作り上げ、共に正しさを求め合い、正しさゆえの強さを修得するよう心掛けることが合気道の稽古における要諦である。
以上の心掛けで稽古を続けることは受けになった者は、より正確な技を仕手(技を掛ける人)ができるよう心掛けることが要求される。つまり相手に対する思いやりの気持ちをその中から培うのである。同時に、最も正しい受けを取ることは、技が極まり、辛い状態を要求される。それにあえて心身を置くことによって耐える心も養えるのである。最も弱い状態で受けを取ることは、一番弱い部分を鍛えることにもなるのであ
る。受けが正しい受けを取ることにより、正しい技が身につけられる仕手は、感謝の心を生じ、交代した時に自らも相手に対して正しい受けを取るようになる。これが謙譲の心の醸成につながるのである。これもまた「対すれば相和す」の合気道心理の大切なところである。日常生活における感謝、おもいやりを技の反復稽古の中で培うのである。同時に気働きの稽古にもつながっている。
われわれが師に仕えていた時、今、師が何を求めているのか、何をしようとしているか、と気を配ったものである。煙火―火、灰皿という関連、また風呂における湯加減―背中の流し等々、道場以外においても常に心掛けることによって気の訓練はでき、いざ稽古の時も活きてくる、この逆も真である。
ここに合気即生活といわれる所以がある。合気道を生活に活かすのではなく、合気そのものが生活であり、生活そのものが合気である事が大切なのである。
4.合気道の理合
理合(りあい)とは、合気道の技法の核となる、理にかなった体の動きのメカニズムのことである。
ア)円運動-求心力と遠心力
合気道の動き(技を施す動作)の中には直線的な運動はほとんどないといってもよい。足捌き、上体の移
動、あるいは腕の運動などは大小の円周上を弧を描いて行われ、さらに立体的に構成されて、それは球体を描いたりある時は螺旋運動を行うものである。ここにも、合気道が相手の力を利用して技を施すという特徴をみることができる。
円運動(同時に球運動)が働くところに自ずと具現する力が求心力であり、また遠心力である。回転するものは、例えば台風や渦潮のように全てのものを引き込む力(求心力)を得ると同時に、互いに回転するコマのように、激しく反発しあう力(遠心力)を与えられる。顕著な技として、正面打入身投げが上げられる。合気道の技にはこの原理が巧みに活かされており、ほとんど一瞬にして極まってしまう技を分析することにより、また、自らが正しく施される技の中に身を投ずることによりよく理解することができるのである。まして、円運動には止まる所がない、直線的動作の中で一旦止って、再度動き出すには、倍のエネルギーを要するが、円運動の延長ではその必要はない。力の省エネにも通じるのである。相手の体勢を崩した状態を戻すことなく、なおも崩しさることができるのである。
ここに、無理のない動きと云われる合気道の特徴、要諦が含まれているのである。
イ)スピード
これは何にもまして重要なことといってもよい。どの様に変化する相手に対しても合わせて動きうるためには、相手に優るスピードある動きができなければならない。今かりに時速100キロの列車に飛び乗ろうとすることは至難の技であるが、その隣を同方向に同時速で走る乗り物があれば、それに乗ることによって相対的スピードはゼロとなる。つまり、互いに静止しているのと同じ状態になるので、ゆっくり渡ることができれば向うのものを自由に取ることもできる。
しかし、スピードは、相手に対する相対的な、したがって優劣を問われるような面だけが重要なのではな
い。
合気道においては、「いかなる物をも含む速度」つまり、一般に考えられるスピードを超越した異質の、絶対的な速度こそ重要なのである。
そこで大切になるのが「気」の働きである。テレパシーに依ってあらゆる事を見透かしたり動かしたり、感じたり等ということを聞くことがあるが、このテレパシーのスピードはどうであろうか。遠隔の地においても瞬時に考えてることが伝わってしまう、あるいは状況が判ってしまう事は、不可思議この上もないことである。
しかし、宇宙的感覚で考えたとき、驚くことでもない。宇宙即地球即物即人即我、総て一つであり、その物々を包括しているのが「気」である。「気」が一つの物であるならば、相手の気も自分の気も一つであり、そこには距離もスピード感も必要としない。まさに合気した状態である。その境地に一歩でも近づく為に修業をするのである。
ウ)タイミング
相手の動きに自らを合わせることであり、合気道の精髄である。これは運動のスピードや次いで述べる集中力等に密接に連携していることであるが、相手の出る動き、引く動作に自らを合わせることは簡単なことではない。タイミングの取り方も遅れれば相手に押し込まれてしまうし、早すぎれば相手はこちらの動きを察知してそれに対する手段を取って来るという様に、タイミングの取り方のタイミングが大切になる。打って来る相手の力の流れに自分の流れを合せるタイミング、ここぞという時に技を掛けるタイミング、相手が飛びかかって来た時に、それを外すタイミング、また逆にそれを迎えるタイミング、どれを取ってみてもこれが相手を制する上の大事な基本である。このタイミングの取り方も一朝一夕では、できない。日頃の訓練の結果、無意識的に行われた時、初めて強烈な効果を発揮するわけで、意識してタイミングを取ろうとしている間は、上手くいかないことが多いのである。
ある日、電車(山手線)から降りようとした時、何かを感じて降ろしかかった右足を再度上げると、ホームにいた労務者風の男が足払いを掛けて来ていたのだ。勿論その足は空を切り大きく体勢を崩して私の前に背中を向けたので、ポンと突いてやると大きくよろけながら電車の中へ倒れ込む様に入っていった。同時にドアが閉まり、振り返った男は、硝子を叩きながら何か文句を言っていたが私は何事もなかったように歩き出した。これなども、タイミングが悪かった場合は足を蹴られて、前に倒れていたかも知れない。無意識のうちにタイミングが合っていたのだ、あるいは気を察知していたのかも知れない。そこで気配を感ずるということで、次の様なことがあった。
研修生になりたての頃、まだ合気道そのものに、というよりも塩田先生に対して絶対という気持ちになり切って居なかったと思う。
お客様が見え、合気道の説明の受けを取っていた時、眼の前に塩田先生の背中があった、瞬間、どうしたものか、打って大丈夫かという思いが頭に過った。しかし、ままよと後頭部めがけて打ち込んでいくと、そこに塩田先生の姿はなく、足を払われていた。つまりふっとんでいた。
殺気という言葉もあるが、まさに何かの気配を察知して体を捌かれたのだ。
塩田先生が植芝翁のお供で汽車等に乗った時、翁は鉄扇を塩田先生に渡し、何時でも隙があったら打ち込んで来なさいといって居眠りをする。大分眠りが深くなったころを見計らっていざ打ち込もうとすると、頭を上げて「まだかな?」という。またコックリ、コックリとするので、打ち込もうとすると、「何処や」という。何度か試みるうちに諦めて一緒に眠ってしまったそうである。後で翁に聞くと『神様が「塩田が打とうとしているぞ」といっとった』とか、「何か頭がもやもやとして眼を醒ましただけじゃ」というようなことであった。けっして隙を見せずに眼を瞑っていた訳ではない、それでは身が持たない。自然の状態の中で身体自体が「気」に包まれ、気を発し、気を受けているからにすぎない。
気を配ると書いて気配と云うのであるが、修業も積むことによって、ことさら何時も気を配らずとも、自然と気配を感ずるまでになるのである。勿論、天性に備わった人もいるかも知れない。否、人間誰しもが隠れ持っている第六感というものである。それも修業によって気付き、しかも自由に使いこなすまでになるのである。勿論、一朝一夕にできるわけではないが、そのような境地に到達すべく修業に励むのである。気配ということで、もう一つ身近な経験を先日した事がある。
稽古の場合、技の見本の相手をしてもらう時、その日の稽古者の中で一番先輩格の人に受けを取って貰うのであるが、その日は何かを感じ、後輩の方を選んで相手をしてもらった。後で判ったことだが、その先輩格は、前日怪我をして腿を傷めていたのだ、もし名指しされたらどうしようと不安な気持ちで居たそうであ
る。なるほど顔を見た瞬間、あまり良い雰囲気を感じなかったのは(-)マイナスの気が彼の周りを取り囲んでいたのだ。
その気の感じたままを行動に移したのが正しかったのである。
全ての面で、この様に気を感じ取れるようになると、素晴らしい毎日が迎えられるようになるであろう。
「気」が合う等ということも、まさにタイミングそのものである。相手が打ち込んで来た瞬間、摑んで来た瞬間に少しのずれが有っても技は極まらない。
日常生活における、あらゆる事にも当嵌まる。扉を開けた時に入らなければ、入れない。会話においてもしかり、挨拶を取ってみてもタイミングが大事である。その他、数え上げるとキリがない。
つまり、調和のとれた状態をいうのであり、人間関係や自然との関係も常に調和が保たれている事が大切なのである。
エ)集中力
これは持てる力を必要とするところに集めることである。例えば右手で当て身を入れる場合には、左手に力を入れても意味がない。また、相手の手首をつかんだなら、そのつかんだ部分に力を集中することである。
人間自分の持てる力を集中的に1ヶ所に集めて使うことは、なかなかできることではないが、訓練によってレベルの向上が見られるようになるものである。だが、修練を積まない者でも、一旦緩急の際には、信じがたいほどの力を発揮することがある。火事場の馬鹿力ということがいわれるが、実際に目撃したことがあ
る。
戦時中であったが、空襲になり、家財道具を防空壕に収納する段でのことである。さして力のない母親が、タンスの引出しに物を入れたままで窓から手渡すのである。外で受け取ったものの、あまりの重さに驚いていると「早くしなさい!」と叱声が聞こえ、次の引出しを持ってきていた。慌てて運び続けたものであっ
た。空襲も終わり、元に戻すとき、窓の外から手渡すことになるのだが、そんな重たい物は持てないというのである。では、一体先程の力は何だったのか、まるで異った人物が手助けに来ていたかの様であった。実際に目の当たりにしたこの状況をどう説明して良いのか判らない。がしかし、人間には計り知れない無尽蔵の力を秘めていることを実体験したのである。
では、普段その力を引き出し使いきるにはどの様な方法が有るのだろうか。何時も、火事場に遭遇する訳にもいかない。つまり、その様な精神状態を作ることであろう。
夢中になること、吾を忘れること、必死になること、いずれを取ってみても吾という現実のままでは不可能のようだ。
気が付いたら・・・をしていた等と云う話を聞く、まさにそれであろう。
しかし、武道においては、そのような計りしれない力を存分に使いきる丈の修業を求められるのである。
合気道の場合には、集中力を養う独特な訓練が、基本動作および技法の中にある。
オ)重心の移動
一方にある重心を他方に移したり、何割かずつ掛け合ったりすることであり、それによって技の威力を倍加させるものである。
重心の乗った動作ほど、その技の効果は大きく、また、重心の移動をしながら施した技は、それを行なわなかった場合よりもはるかに多くの影響を相手に与えるものである。運動の過程での重心の移動は、それに十分に耐えうる柔らかく強靭な足腰を作ることにもなる。強い足腰は強力な技を生む重要な要素でもあるの
で、基本動作の中には、重心の移動の部分が大きい比重を占めている。稽古に際しては充分心して行うべきである。
カ)呼吸法
日常生活において「呼吸が合う」という言葉が聞かれる。相手と呼吸が合わなければ、何事も成就しない
し、息が上がってしまう。
技においても同様で、相手と呼吸が合えば、制するのに易く、呼吸が合わないと相手に乗ぜられる。つまり気を合わすこと、合気である。気を合わせ、力を合わせて技を施すのである。合気道においていわれる「呼吸力」とは、稽古によって得られる気力の入った力、身体全体から出る力を一点に集中し活用する力、つまり集中力等の総称である。
それを体得する一つの方法として、座り技両手持ち呼吸法が行われる。お互いに正座をして相手の引く力
(押す力)に合わせて両手を振りかぶり、相手を浮かして切り崩し、後方に倒して、姿勢を整えて気力で押える。あくまでも相手に合わせ、しかもなお両腕に充分呼吸力を出す。特に最後は、身体全体の呼吸力と気で抑えることのできるよう稽古をするのである。
生物は、自然に呼吸をし、外界から酸素を体内に取り入れ、炭酸ガスを排出して生命を維持していることはいうまでもないが、合気道ではこの吸う息、吐く息とともに止める息を含めた三段階のリズムが力の集中に大きく関係し、また、動きに伴う疲労度にも影響を及ぼす重要なポイントになっている。息を大きく吸う
か、小さく吸うか、また大きく吐くか、小さく吐くかその間に息を止めるか、動作によって異ってくる。ある一つの技を掛ける場合を考えると、技を掛ける前に息を吸い、技を掛けるときは息を止め、掛けおわって息を吐くというのが典型的なパターンである。つまり、力を一点に集中しようとすれば、当然息を吸う、あるいは吐く動作と力を一点に集中する動作が併行的に行われるから、集中力が弱くなってしまう。であるから、真に力を一点に集中しようとすれば、息を止めてそれだけの動作にしぼるのである。しかし、息を止める時間が長いと、その間、体内の酸素の欠乏度が高まり、それだけ多く酸素を補給せよと身体が要求し、すぐ肩で息をせざるをえなくなる。これが疲労に通じる。
息を止める時間が短ければ、短いほどいいので、合気道の技が一瞬にして極めるというのもそこにある。集中力が最高になるのも一瞬で、だらだら長く最高の集中力を維持することは不可能である。
音楽のリズムと同じように、技の一つ一つ、あるいは技の連続の中で呼吸の律動が無駄なく配分されたと
き、つまり、自分の身体がリズムに乗ったとき最も楽に身体が動き、最高の集中力が発揮され技の効果も大きくなるのである。ただし、集中力の効果も大にするには、先に述べた安定した身体の重心も深く関係してくることはいうまでもない。また、息を吸うということは、気を吸うことでもある。しかし、気は溜めるものではない。
気は出すから入ってくるのである。天地(宇宙)の気と人間が交流することを「息」というが、息が一時的に途絶えれば気絶をする。永久に途絶えてしまえば死ぬ。つまり、天地の気と人間の気の交流が止まったときが死である。
人間は生きている間は、何時も気を出していなければならない。気を出すから新しい気が入って、出しているから天地と交流して「生きている」実感があるのである。呼吸の意味がそこにある。
稽古をしている者で、肩で息をゼイゼイしているのは、疲れは勿論であるが、大きな理由は息を吸いすぎ
て、吐く量よりも胸につかえる方が多いために来るのである。つまり、呼吸法が自然ではないからである。この様な時は、大きく息を吐くと良い。中を空にすると、自然と必要な分だけ入るのである。
少年の水泳教室で、自然の大切さを教えていたのである。自然にあった呼吸法から、強力なる呼吸力と集中力が出てくるのである。しかし、この呼吸力、集中力を修得することは、口でいうほど容易ではない。絶えざる稽古と研究の中で自分の吸う息、吐く息、止める息の強弱、長短と速やかな重心の移動と、バランスがとれ、自分の体がリズムに乗るかを体得することである。
その時こそ、体が軽く楽に動き、しかも技の効果が大きく、疲労度も少ないことがわかり、合気道のすばらしさを自覚し、一層修業の楽しさが増すのである。
楽しむ気、つまり気楽に行動する事、リラックスにつながってくるのである。
キ)動中に静を持す
禅は、静中に静を求めるとすれば、合気道は動中に静を持することである。合気道の技には当然動きがあ
る。どの様な動き、また、相手の力に逆らわず、時にはその相手の力を誘導するだけでむしろ相手の力を自分に取り入れて、また、時には自分に取り入れた相手の力に、少しの自分の力を添えて制するのである。
この間、瞬時でも素直な心を失うと、相手の動き、相手の力の流れを見失い、それとぶつかり合ったり、ずれたりして、技の効果を殺してしまうことになるからである。
この場合自分の方が力が強ければ、その力で相手を捩じ伏せられるかも知れない、それは、合気道で制したのではなく、力で勝っただけである。
動中に静を持してこそ、相手の動き、相手の力の流れが良く見えてくるのである。
5.対すれば相和す
剣術家・鬼一法眼の言葉とされているが、合気道は、相手と気を合わせる武道である。つまり、力の揉み合いをしない、押されれば押し返さない。引っ張られたら引っ張り返さないで相手と相和す。これも、合気道の大切な基本の一つであ
り、ここにも先に述べた素直な心がなければ、相和すことが出来ないのは勿論である。和は、妥協ではなく適合なのである。相和すことによって相手と一体となって、一つの流れになり、両者の力が衝突し合わないから、無理な力を要せずして技が施せるのである。非力な女性でも、少年でも、高齢者でも合気道を続けられるのはこの為である。
合気道はそもそも自分の方から人に攻撃を掛ける武道ではなく、護身術であるから、相手の出方に応じて相和すことができるのである。
常に相手の力の流れが先にあるからこそ、その動きを自分の体の動きに合うように誘導して技が掛けられる。
合気道の基本の一つであるこの「対すれば相和す」を、すべての人の生活の基本にすれば、世の中の争い、相克は亡くなると思うのである。
吾が師、塩田剛三が、常にいわれている、和の武道である合気道を通じて、人の和、民族の和、ひいては世界平和に寄与するという夢を実現する為に日夜精励努力しているところである。
更にさらに「気」を横溢にして・・・。





